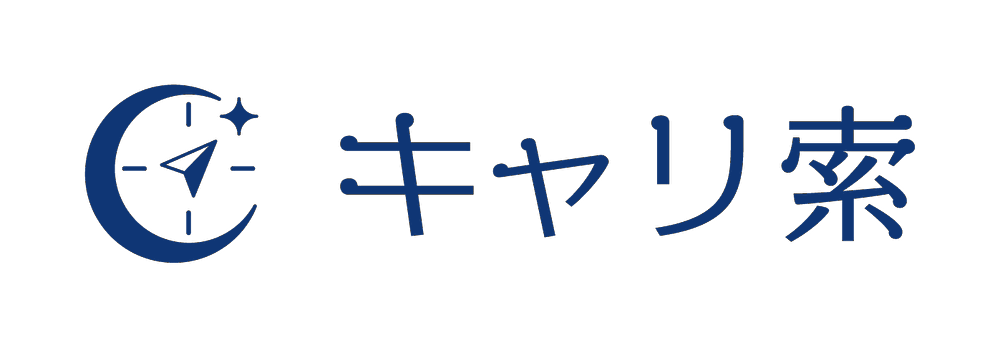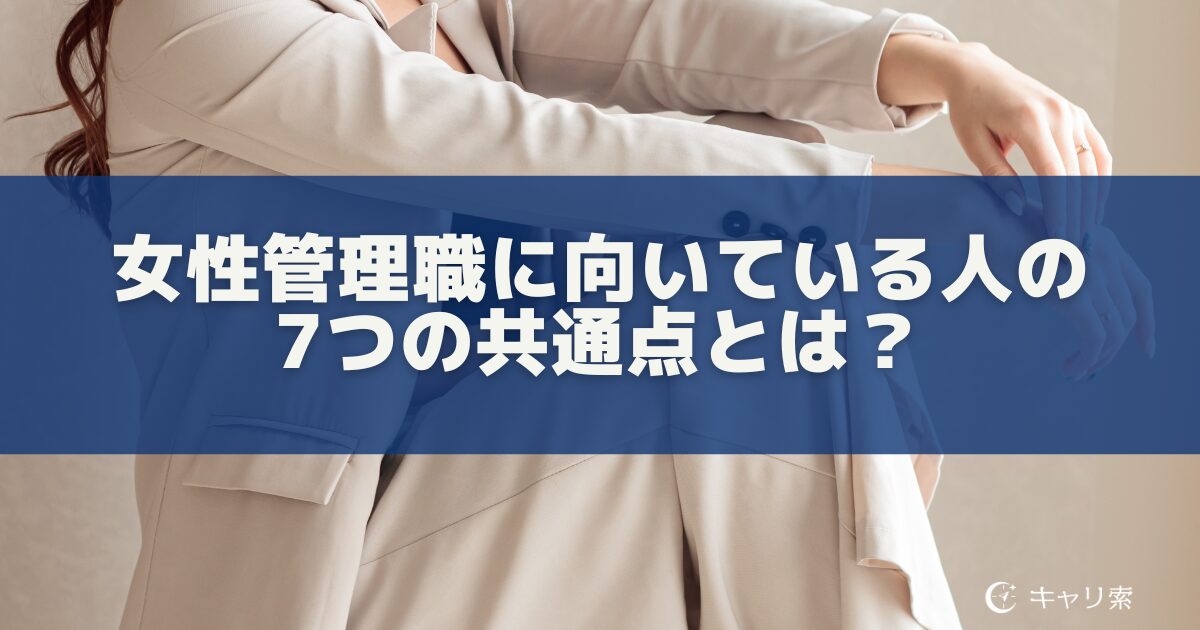「女性の管理職が少ない中、管理職に抜擢されたけど、自分に務まるか不安…」
「女性の管理職ってどうなの?自分は管理職に向いている?」
「子供や家庭を抱えている中、責任が重そうで心配」
管理職に就くというのは、やりがいや成長のチャンスがある一方で、特に女性にとっては不安やプレッシャーも感じやすいポジションですよね。
周囲にロールモデルが少ないと、なおさら「自分に向いているのか?」と悩んでしまうこともあると思います。
でも実は、管理職として活躍している女性たちには、共通して備わっている“ある特徴”があるんです。特別な才能ではなく、日々の考え方や行動がカギなんですよ。
この記事では、管理職に向いている女性の特徴や考え方を、実体験や具体例を交えながらお届けします。
子育てをしながら正社員で働き続けているワーママの筆者が、現場目線でリアルに解説していきます。
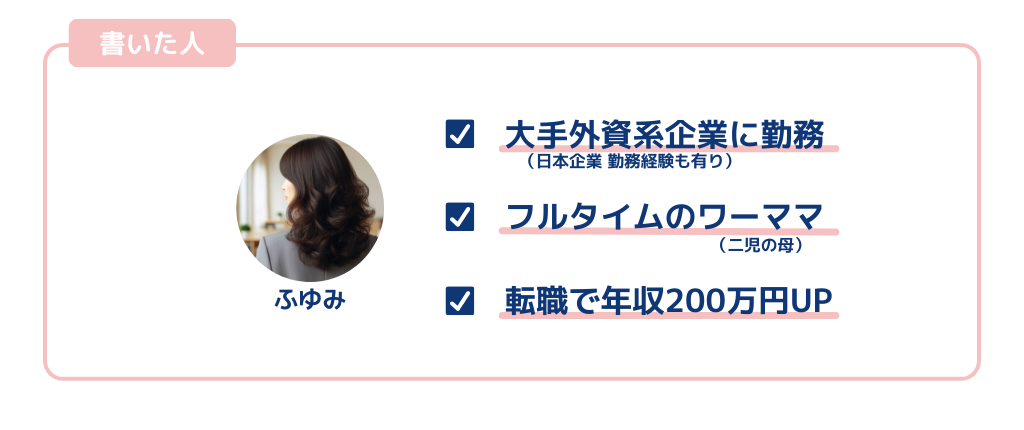
中途採用は新卒採用とは違い、ポジションが空いた瞬間や事業拡大など「今だけ」のタイミングで募集が出るケースがほとんど。
つまり、「理想の求人が出たら転職したい」と思っている人ほど、転職エージェントに登録しておくことが重要です。応募は断れますが、締切後の求人には二度と申し込めません。

待っていても”いい情報”は手に入りません。まずは登録しいい求人が届く状態をつくっておくことが、後悔のない転職の第一歩です。
▶︎車や家の購入で複数社の相見積もりを取るように、転職エージェント選びも比較が大切
複数のエージェントに登録しておくことで、担当者との相性、紹介される求人の幅、非公開案件の種類など、しっかり比較でき、納得できる転職が叶います。
理想の求人は、行動した人にだけ届きます。無料のサービスなのですから、後悔しない転職のためにいまの自分にできることを始めておきましょう。
| 転職サービス | 特徴 |
JACリクルートメント | 年収を上げたいなら 登録しておきたい 満足度高いワンランク上の転職 \ 筆者イチオシ / 求人を見る |
ビズリーチ | 市場価値を知るなら 登録しておきたい 登録だけでスカウトが届く 求人を見る |
リクルートエージェント | 業種職種年代問わず 登録しておきたい 圧倒的求人数で情報収集にも◎ 求人を見る |
女性管理職に向いている人とは?まずは特徴を知ろう
管理職と聞くと、「自分にはちょっと荷が重いかも…」と思う人もいるかもしれません。
特に女性の場合は、仕事だけでなく家庭や育児など、さまざまな役割と両立しながらのキャリアになることも多く、「管理職ってどんな人が向いてるの?」という疑問を持つのは自然なことです。
ここではまず、“管理職に向いている人”とはどういうタイプなのか、そして女性ならではの強みが活きる場面について解説していきます。
管理職に向いているとは?
そもそも「管理職に向いている」とは、どのような状態なのでしょうか?
それは、完璧なリーダーである必要はなく、周囲と信頼関係を築きながらチームを前進させていける人のことを指します。声が大きくて強いタイプである必要も、全ての知識を網羅している必要もありません。
たとえば、部下が悩んでいるときに話を聞いてあげられる。判断が難しい場面でも、情報を集めて冷静に考え、納得できる決断ができる。こうした「人の気持ちに寄り添える力」や「物事を前に進める力」は、まさに管理職に求められる資質です。
さらに最近では、「チームを支える調整役」「縁の下の力持ち」としてのリーダー像も評価されるようになってきています。
だからこそ、“自分は管理職に向いてないかも”と感じている人ほど、実は向いている可能性もあるんです。
管理職は女性ならではの強みが活きる場面も多い
女性だからこそ活かせる“強み”が、管理職の現場では実はたくさんあります。
特に、共感力や気配り力といったソフトスキルは、チームをまとめる上で非常に有効です。
たとえば、チームメンバーがミスをしたとき、「なぜそうなったのか」を頭ごなしに責めるのではなく、まずは話を聞き、背景にある問題を丁寧に探ろうとする姿勢。これは、信頼関係のある組織づくりには欠かせないアプローチです。
また、女性管理職がいることで、女性社員や若手の社員が「相談しやすい」と感じることも多く、職場全体の風通しが良くなる傾向もあります。
男性中心の組織がまだまだ多い中、女性ならではの“チームへのまなざし”が価値を発揮する場面は少なくないのです。
管理職は性格や資質だけで決まるものではない
「私は引っ込み思案だから向いていないかも…」と思っている方も、安心してください。管理職として成功している人すべてが、もともとリーダー気質だったわけではありません。
管理職に必要なのは「性格」よりも「考え方」と「姿勢」です。
たとえば、失敗したときに「自分のせいかも」と一度立ち止まって考えられる謙虚さや、周囲からのフィードバックを素直に受け取って行動に移せる柔軟性は、性格に関係なく身につけられる資質です。
また、管理職といってもそのスタイルはさまざまです。
「前に出て引っ張るタイプ」もいれば、「陰で支えるまとめ役タイプ」もいます。自分らしいやり方で、チームや周囲に良い影響を与えられるなら、それが立派なリーダーシップだと思って良いんです。
向いているかどうかは“固定的な要素”ではなく、“これから身につけていけること”だと考えると、ぐっと気が楽になりますよね。
女性管理職に向いている人の共通点7つ
管理職として活躍している女性には、ある共通点が見られます。
それは、決して特別な才能や肩書きではなく、日々の仕事の中で培われたスキルや考え方。「自分には向いていないかも…」と思っていた人が、気づけばチームに欠かせない存在になっていた、ということもよくあります。
ここでは、実際に管理職として信頼を集めている女性に共通する特徴を7つご紹介します。
女性管理職に向いている人①コミュニケーション能力が高い
管理職としてチームをまとめるうえで欠かせないのが「コミュニケーション能力」です。これは単に「話すのが得意」ということではなく、「相手の気持ちを汲み取り、信頼関係を築く力」でもあります。
たとえば、部下がミスをして落ち込んでいるとき、すぐに責めるのではなく、「何があったのか、詳しく教えてくれる?」と、まずは冷静に耳を傾ける。
このような姿勢は、チームに安心感を与えるだけでなく、「この人のもとで働きたい」と思ってもらえるきっかけにもなります。
日々の業務でも、たとえば「お疲れさま、今日の○○すごく良かったね」といった一言があるだけで、部下のモチベーションはぐっと上がります。
ちょっとした気配りや声かけができる人は、それだけで職場の空気を和らげ、円滑なコミュニケーションの中心的存在になれるんです。
また、業務連絡ひとつとっても、「○○しておいてください」ではなく、「○○を進めてもらえると助かります」と丁寧に伝えることで、相手の受け取り方は大きく変わります。
言葉選び一つで、チームの雰囲気や協力体制が変わってくる。そこに気づいて行動できる人は、まさに管理職向きと言えるでしょう。
私自身、最初の頃は「もっと強く言わないといけないのかな」と思っていた時期もありました。
でも、部下との距離が縮まったのは、むしろ“やわらかく伝えること”を意識し始めてから。感情的にならず、相手の話に耳を傾ける。それだけで、会議や1on1の雰囲気もぐっと良くなりました。
そしてもう一つ大切なのが「聞く力」です。
部下が安心して相談できる環境を作るには、傾聴の姿勢が欠かせません。うなずきながら、相手の言葉を繰り返して確認したり、否定せずに受け止めたりするだけで、信頼感はどんどん積み上がっていきます。
こうした積極的なコミュニケーションの積み重ねが、「この人と働きたい」「困ったときは相談しよう」と思わせる管理職をつくっていくんですよね。
女性管理職に向いている人②感情のコントロールが上手
管理職という立場になると、冷静さが求められる場面が一気に増えます。
部下のミス、上層部からのプレッシャー、予期せぬトラブル…。そんなときに、感情的にならず、状況を俯瞰して判断できる人は、まさに「管理職に向いている人」です。
特に女性の場合、「感情的になりやすい」といった先入観を持たれることもあり、不本意ながらそう見られてしまうことも少なくありません。
だからこそ、感情をうまくコントロールし、冷静に対応する姿勢は、周囲からの信頼を大きく高めるポイントになります。
たとえば、筆者があるプロジェクトで予算の大幅カットを告げられたとき、内心ではかなり焦りました。
でも、その気持ちを顔に出すことなく、まずは状況を整理し、「今できることからやろう」とチームに声をかけました。すると不思議とチームも落ち着きを取り戻し、前向きな提案が次々と出てくるようになったんです。
逆に、管理職が感情に振り回されると、チーム全体が不安定になります。
「上司の機嫌が読めない」「言ってることが毎回違う」と感じさせてしまうと、信頼関係にもヒビが入ってしまうんですよね。
もちろん、人間なのでイライラしたり落ち込んだりすることはあります。
でも、それをそのままぶつけるのではなく、「一度深呼吸してから言葉にする」「その場で判断せず少し時間をおく」など、自分なりの“感情の整え方”を持っておくと、管理職としての対応力がぐっと上がります。
そして、そうした姿勢は、部下たちにも良い影響を与えます。「リーダーが落ち着いてるから、自分も冷静に考えよう」と自然と空気が整います。
感情を押し殺す必要はありませんが、必要な場面で“感情と距離を取る力”がある人は、チーム全体を落ち着かせ、前に進めることができる存在になれるでしょう。
女性管理職に向いている人③相手の立場に立って考えられる
管理職として大切なのは、ただ指示を出すのではなく、相手の背景や状況を理解しながら行動できること。
つまり、“相手の立場に立って考えられる”力がある人は、周囲との信頼関係を築きやすく、チーム運営もうまくいきやすいんです。
たとえば、ある部下が仕事の進みが遅れていたとき、「なぜまだできていないの?」と問い詰めるのではなく、「最近ちょっと忙しそうだけど、何か困っていることある?」と声をかけられる人。こうした姿勢は、部下にとって大きな安心材料になります。
実際、私も以前、納期ギリギリの案件を抱えていたメンバーに対し、「何が一番負担になってる?」と聞いたことで、本人も気づいていなかった根本的な課題が見えてきたことがありました。
結果的に周囲のフォローでうまく解決でき、「ちゃんと見てくれてるんですね」と言われたときは、正直うれしかったです。
また、立場が変わると、見える景色も変わってきます。
上司としての立場、チームリーダーとしての責任、そして部下としてのプレッシャー…。それぞれの視点に立って考えられる人は、会議でも調整役として頼りにされやすいんですよね。
大切なのは、「正しいことを言う」ことではなく、「相手に伝わる形で伝える」こと。そのためには、まず“どんな状況にいるか”を想像する力が必要です。
たとえば、家庭と両立しながら働いている部下に対して、「もっと残業してよ」と言うのではなく、「日中に集中して進める方法を一緒に考えよう」といったように、相手に寄り添った提案ができるかどうか。
こういった配慮の積み重ねが、「この人のために頑張ろう」と思わせる上司像につながっていくんです。
つまり、“人の気持ちを理解しようとする姿勢”がある人は、自然と周囲から信頼される存在になっていきます。
女性管理職に向いている人④問題解決思考を持っている
管理職として信頼される女性には、“問題を前向きに乗り越える力”が備わっています。
それはただ冷静に判断できるというだけでなく、「状況に応じて柔軟に対応できる力」や「関係者の気持ちに配慮しながら解決へ導く力」を含めた、“女性ならではの問題解決力”が光る場面が多いです。
たとえば、部署間の連携がうまくいかずに仕事が滞っているとき。その原因が人間関係のちょっとしたすれ違いだったりすることもありますよね。
そういうとき、男性だと「とにかく話し合って解決しよう」と力技になりがちですが、女性は相手の感情や立場に気を配りながら、ほどよいタイミングと距離感で歩み寄る調整役になれることが多いです。
私自身も、営業と制作の間で調整ミスが起きたとき、最初にしたのは「誰が悪いか」を探すことではなく、それぞれの視点で何が起きていたのかを丁寧にヒアリングすることでした。
それによって感情的な対立は避けられ、お互いの立場を理解し合った上で、再発防止の流れを作ることができました。
また、女性は同時に複数のことを考えながら行動するのが得意と言われています。
チームの進捗状況だけでなく、部下のコンディション、他部署の動き、家庭のことなど、さまざまな視点をバランスよく見て判断できるのも大きな強みです。
加えて、「相談しやすい雰囲気」を自然に作れるのも女性管理職の魅力。
「こういう話をしてもいいんだ」「ちゃんと聞いてくれるんだ」という安心感が、メンバーの小さな不安や違和感を早めにキャッチする助けにもなります。これは、トラブルの芽を事前に摘むという意味でも、立派な“問題解決力”なんですよね。
問題が起きたときに、「どうして?」と感情をぶつけるのではなく、「どうしたらうまくいく?」と建設的に考えられる。しかもそれを、周囲の感情に配慮しながら、落ち着いたトーンで進められる人は、間違いなく管理職に向いていると言えるでしょう。
女性管理職に向いている人⑤周囲と協力しながら進められる
管理職に求められるのは、“自分ひとりで頑張る力”よりも、“周囲と力を合わせて物事を前に進める力”です。
その中でも、女性が得意とする「協調性」や「気配り」は、まさにチームを動かす潤滑油のような存在。
たとえば、チーム内で意見がぶつかってしまったとき。
どちらかが一方的に正しいと決めつけるのではなく、「それぞれに良さがあるよね」と、一度受け止めたうえで、バランスを取りながら着地点を探せる人は、管理職として非常に重宝されます。
私の経験でも、チーム内で方針が割れたとき、「一旦整理してみようか」と各メンバーの立場や意見を見える化したことで、「じゃあこの方向でやってみよう」とスムーズに合意形成ができたことがありました。強引にまとめるのではなく、自然に“納得感のある協力体制”を作ることが、結果的にチーム力を高めることができます。
また、女性は人の得意・不得意をよく観察している人が多く、「この作業なら○○さんが得意そう」「ここは△△さんのサポートが必要かも」といった“役割の組み合わせ”が上手な人が多いです。そうしたチーム全体を見渡して調整できる力は、協力体制を築くうえで欠かせません。
さらに、家庭や育児との両立を経験している女性管理職ほど、「みんなで助け合わないと回らない」という現実を肌で理解しているもの。
だからこそ、「この仕事、手が空いた人で手分けしよう」「今日だけ○○さんにお願いしていい?」と、自然な連携を生み出す工夫ができるんです。
協力というのは、単に「みんな仲良くやろう」という話ではありません。
誰がどこで力を発揮できるのかを見極め、それぞれが気持ちよく動けるように配慮しながら、チームとして成果を出すこと。そこに長けている女性は、間違いなく管理職に向いています。
女性管理職に向いている人⑥決断力と責任感がある
管理職にとって避けて通れないのが、“決断する場面”です。
情報が出そろっていない中でも、限られた時間の中で選択し、チームを前に進めなければいけないことが多々あります。そんなとき、「誰かが決めてくれるのを待つ」のではなく、「自分が責任を持って決める」と踏み出せる人は、確実に管理職に向いています。
とはいえ、「決断力」と聞くと、「即断即決できる人」「リーダー気質の人」だけが当てはまるように感じるかもしれません。でも実際は、“自分の選択に責任を持つ覚悟”さえあれば、即決型でなくてもまったく問題ありません。
たとえば私が関わったある女性管理職は、決して言葉数の多い人ではありませんでしたが、会議の場では「私はこの方向でいくべきだと思います」と、しっかりと理由を添えて結論を伝えていました。
その落ち着いた態度と筋の通った判断は、むしろ周囲に安心感を与え、「この人の判断ならついていこう」と信頼されていました。
また、女性は「まわりにどう思われるか」を気にして、責任のあるポジションに一歩踏み出せないこともあります。
ですが、実は家庭や子育てと向き合ってきた経験そのものが、自然と“責任感”を育てていることも多いんですよね。
「任されたからには、やりきろう」
「ミスがあったら、自分ごととして向き合おう」
こうした誠実な姿勢は、表立っては見えにくくても、確実に評価されるポイントです。
そしてもうひとつ大切なのは、「決めたあと、周囲を巻き込んでいけるかどうか」。決断したことに責任を持ちつつ、必要があれば見直しも厭わない柔軟さ。そうした姿勢があれば、どんな局面でもブレずに前に進める管理職になれるはずです。
女性管理職に向いている人⑦柔軟な働き方への理解と実践
これからの時代、管理職に求められるのは「成果主義」だけではありません。
働く人それぞれの事情や価値観に寄り添い、多様な働き方を受け入れながら、チームとして最大限の力を引き出す“柔軟なマネジメント”ができる人が、リーダーとして選ばれるようになっています。
そして、まさにこの“柔軟性”は、女性管理職が最も力を発揮できる部分のひとつです。
たとえば、育児中の部下が「保育園の送り迎えで17時までしか働けない」と言ったとき、「じゃあその中で成果を出せる方法を一緒に考えよう」と、働き方そのものに視点を広げて対応できる管理職は、信頼を集めます。
単に“時間”で評価するのではなく、“成果”や“プロセス”を丁寧に見る姿勢があるからこそ、部下も安心して働けるのです。
私自身も、子育てと仕事を両立する中で、「朝は子どもの準備でバタバタ」「夜は残業が難しい」といった現実と日々向き合ってきました。
だからこそ、時間の制約があるメンバーの事情にも共感でき、「じゃあ○○のタスクは分担しよう」「資料作成はリモートでOK」といった柔軟な対応が自然にできるようになりました。
さらに、働き方だけでなく「人それぞれの価値観」への理解も大切です。
「がむしゃらに出世したい」人もいれば、「仕事と家庭をバランスよく続けたい」人もいる。そうした個々のスタンスを尊重しながら、それぞれに合った成長機会を与えられる人は、まさに次世代の管理職と言えるでしょう。
柔軟さとは、甘さではなく「一人ひとりの力を引き出す工夫」です。その視点を持ち、実践できる人は、これからの組織にとって欠かせない存在になっていきます。
女性が管理職に感じる不安とその乗り越え方
管理職になると、責任やプレッシャー、人間関係の変化など、さまざまな不安がついてまわります。
特に女性の場合は、仕事以外にも家庭・育児・周囲の目など、複数の要素が絡み合うため、「やっていけるだろうか…」と感じる人も少なくありません。
でも実際に多くの女性管理職が、不安を抱えながらも現場で活躍しています。ここでは、よくある不安について、どのように乗り越えていけるのかを具体的に解説します。
女性管理職の不安①家庭と両立できるか
女性が管理職をためらう理由で圧倒的に多いのが、「家庭との両立が難しそう」という声。
子どもがいる場合は、保育園のお迎え、病気の対応、学校行事…と、どうしても突発的な予定が入ります。管理職になれば残業や会議も増え、家との両立が物理的にも精神的にも不安になるのは当然です。
ですが最近では、リモートワークや時差出勤など柔軟な働き方を導入している企業も増えています。そういった制度を上司である自分が積極的に活用していくことで、皆が働きやすい会社を作っていくことに貢献することができます。
同じように家庭を持つ部下に対して“理解のある上司”になれるという点でも、女性管理職の存在は非常に重要です。
実際、筆者の以前の上司が女性でしたが、保育園からの突然の呼び出しがあっても時間休を使いながら、業務は在宅で調整。チーム全体に「お互いさま」の雰囲気が生まれ、男性も女性も家族と仕事をやりくりしながら働きやすくなり、部署で雰囲気が一番いいチームと言われていました。
両立に不安がある人こそ、職場の制度や周囲のサポート体制を見直しながら、“できる方法”を一緒に模索することで、会社にも他のメンバーにもいい流れを作ることができるでしょう。
女性管理職の不安②ロールモデルがいない
「社内に女性管理職がいない」「目指したいと思える先輩が見つからない」
これも多くの女性が抱える不安のひとつです。
ロールモデルがいないと、将来の自分がどう働いているのか、何を優先していいのか、イメージが湧きづらくなります。とくに20代後半~30代前半は、結婚・出産とキャリアの選択が重なる時期でもあり、迷いが生まれやすいタイミングです。
そんなときは、社外に目を向けてみるのもひとつの方法です。他社の女性管理職のインタビュー記事を読む、キャリア系SNSでつながりを探す、セミナーに参加するなど、「参考にできる人」を自ら探しに行くことで、新しい視点が得られます。
また、自分自身が“これからロールモデルになる側”だと捉えることも一つの考え方です。
「私がやってみせることで、後輩の背中を押せるかもしれない」と思えたとき、不安は少しずつ希望へと変わっていきます。
女性管理職の不安③失敗できないプレッシャー
管理職になると、「失敗したら自分だけの問題じゃ済まない」と感じる場面が増えます。
判断ミスがチーム全体に影響を及ぼすこともあるため、女性に限らず強いプレッシャーを感じるポジションでもあります。
特に女性管理職の場合、「女性だから失敗した」と言われたくないという思いから、過剰に慎重になってしまう人も少なくありません。でも実際は、完璧な管理職なんていませんし、失敗もまた学びの一つです。
大切なのは、「失敗しないように」ではなく、「失敗しても立て直せる仕組み」を持っておくこと。
たとえば、リスクを事前に共有しておく、判断のプロセスをメモに残しておく、部下にも責任を分担するなど、少しの工夫でプレッシャーを分散させることができます。
さらに、失敗したときに正直に認め、「次はこうするね」と前向きに対応する姿は、部下にとっても学びになります。“強いリーダー”ではなく、“柔らかくて誠実なリーダー”こそが、信頼される女性管理職なのです。
実際に女性管理職として活躍している人のリアルな声
ここまで、女性管理職に向いている人の特徴や不安の乗り越え方をご紹介してきましたが、実際にその立場で活躍している人はどんな風に感じているのでしょうか?
女性管理職として働く日々は、想像よりもずっと濃密で、挑戦の連続です。ここでは、実際に管理職として活躍している3名の女性のリアルな体験を紹介します。
プレッシャーや孤独感を抱えながらも、自分らしく役割をまっとうする姿から、ヒントを得ていただければ幸いです。
「管理職は自由度が増える。だからこそ子育て中に挑戦してよかった」(30代・課長職)
かつての私は、「子どもが小さいうちは管理職なんて無理」と思い込んでいました。
チームの責任を持つ立場になれば、残業や急な対応が増えて、家庭とのバランスが取れなくなると不安だったのです。
でも、実際に昇格してみると、むしろ時間の使い方に自由度が増えたことに驚かされました。
業務のスケジュールを自分でコントロールできるようになり、保育園の送迎や子どもの急な体調不良にも柔軟に対応できるようになったのです。
以前は「すみません」と謝りながら周囲に頭を下げていた場面でも、今では「この時間帯は在宅に切り替えます」と、堂々と判断できるようになりました。
もちろん、責任の重さや判断を求められる場面は確実に増えました。
それでも、日々の業務に対して主体性を持って動けるという意味では、精神的な余裕が増えたとも感じています。
「子育て中だから管理職は無理」ではなく、「子育て中だからこそ、柔軟に働けるポジションに挑戦すべき」——
今では心からそう思っています。
「誰にも弱音を吐けず涙をこらえながら席に戻ったことも」(40代・部長職)
管理職になって一番つらかったのは、周囲に同じ立場の“女性管理職”がいなかったこと。
同じフロアに管理職は何人もいるけれど、全員が男性で、飲み会やゴルフでの情報共有には入れない雰囲気がありました。会議中の空気感や、昼休みの何気ない会話にすら“仲間外れ感”を感じる日々が続いていました。
どんなに忙しくても、どれだけ頑張っても、自分だけが浮いているような感覚。それが心に重くのしかかっていました。
ある日、重要なプロジェクトの最中にトラブルが起きました。
一人で抱え込んでなんとか乗り切ろうとしましたが、内心では不安でいっぱい。トイレに駆け込んで、誰にも見られないようにそっと涙を拭き、何食わぬ顔でデスクに戻ったことを今でも鮮明に覚えています。
「このままでは潰れてしまう」と感じ、社外の女性管理職が集まる勉強会に参加するようになりました。
同じような悩みや孤独を経験している仲間の存在に出会えたことで、自分だけじゃないと思えましたし、肩の力がふっと抜けていくのを感じました。
今では、自分の部下にも「上司だって悩むことがあるんだよ」と素直に話せるようになり、チーム全体の雰囲気もやわらかくなってきました。
管理職という役割に“完璧”を求めすぎず、頼れるところは頼る。それが、長く続けるためのコツなのかもしれません。
「仕事の幅が広がって視野が確実に変わった」(30代後半・企画部係長)
管理職に昇進する前は、目の前の業務をきちんとこなすことに集中していました。
自分のタスクをミスなく終えることが第一で、他部署の動きや経営の方針にまで意識が及ぶことはほとんどなかったように思います。
しかし、係長としてチームを見る立場になってからは、自分の仕事だけでなく、「部下の進捗はどうか」「他部署との連携はスムーズか」「全体としての成果が出ているか」など、あらゆる視点から物事を捉える必要が出てきました。
最初は戸惑いもありましたが、関係者と定期的に情報交換するようになったり、会議で経営層の話を直接聞いたりする中で、「会社全体の流れ」の中で自分たちの仕事がどう機能しているのかを俯瞰して見られるようになったのです。
特に印象的だったのは、マーケティング部との共同プロジェクトに初めて関わったときのこと。
今までは「完成した資料をもとに施策を打つだけ」だったのが、「なぜこの施策が必要なのか」「どの数字を改善したいのか」まで深く理解し、意見を求められる立場になったことで、自分自身の視座がぐっと上がったと感じました。
管理職というポジションは、責任が増える分だけ「見える世界」も広がります。
一歩引いてチームを支える役割だからこそ、自分の業務に閉じこもるのではなく、全体を見渡しながら戦略的に動く——そうした考え方が身についたことは、何よりの財産です。
今では、後輩メンバーから相談を受ける際にも「自分の仕事の先には、こんな意図があるよ」と視野を広げるアドバイスができるようになりました。これは、管理職になって初めて得られた気づきだと感じています。
女性管理職に向いているかを見極める3つのセルフチェック
「自分は本当に管理職に向いているのか」
その問いは、多くの女性が昇進の打診を受けたとき、最初に感じるものです。向き・不向きを完全に判断することは難しいですが、これから紹介する3つの視点で自分を振り返ってみると、“その素質”が見えてくることがあります。
管理職になる前に、自分の中にある「リーダーとしての芽」に気づくヒントとして、ぜひチェックしてみてください。
女性管理職に向いてる特徴①自分以外の視点で物事を考える
管理職は、自分ひとりの視点だけで判断してはいけません。
部下、上司、他部署、クライアント…と、さまざまな立場の人と関わる中で、それぞれの背景や状況を想像しながら物事を進める力が必要です。
たとえば、「この提案を通すには、先方の意図をどう汲み取るか」「この言い方だと部下はどう感じるか」など、相手軸で思考できる人は、自然と信頼されやすくなります。
日常的に「相手の立場だったらどうかな?」と考えるクセがあるなら、それは立派な管理職の素質です。
女性管理職に向いてる特徴②“できない理由”より“できる方法”を探そうとする
想定外のトラブルや制約があったとき、「できないから仕方ない」と諦めるのか、「どうすれば実現できるか」を考えるのか。
この思考の違いが、管理職に向いているかどうかの分かれ道です。
もちろん、すべての問題を自力で解決する必要はありません。
ただ、前向きに“突破口を探す姿勢”があるかどうかが重要です。その姿勢がチームに安心感をもたらし、結果として周囲の信頼を集めるようになります。
日頃から「一歩引いて俯瞰する」「代替案を考える」習慣がある方は、管理職としての“問題解決力”をすでに持っていると言えるでしょう。
女性管理職に向いてる特徴③周囲の力を引き出しながら成果を出すことに喜びを感じられる
管理職とは、自分の手で直接成果を出すポジションではありません。
部下やチームの力を引き出し、全体をまとめ上げて結果を出す——その“裏方的な役割”に喜びを感じられるかどうかも、大切な要素です。
「部下が育ってきた」「自分が動かなくても成果が上がった」そんな状況に満足感を持てる人は、チーム全体を見渡す“マネジメント視点”を自然と持っている証拠。
人の成長やチームの調和を嬉しいと感じるあなたは、まさに管理職向きの思考の持ち主です。
女性が管理職として活躍するために大切なこと
「女性が管理職として活躍するには、何が必要ですか?」
多くの方から寄せられるこの問いに、シンプルに答えるとすれば——
それは、“自分らしく、誠実に向き合い続けること”に尽きます。
確かに、女性が管理職として働くには、まだまだ課題や壁もあります。
ライフステージの変化、ロールモデルの不在、性別による偏見…。
それでも今、多くの女性たちがそれらを乗り越え、しなやかに組織を支え、導いています。
重要なのは、誰かの理想像を目指すことではなく、“自分なりのスタイル”を確立していくこと。
チームを一人で背負い込むのではなく、周囲と支え合い、時には頼り、学びながら進んでいく——
そんな等身大のリーダー像こそ、今の時代に求められる管理職の姿です。
また、女性が管理職になることは、単なる「ポジションの昇格」ではありません。
それは、後輩女性にとってのロールモデルとなり、組織全体の価値観や文化を変えていく大きな一歩でもあります。
「自分にはまだ早いかも」「うまくやれる自信がない」
そう感じることがあっても大丈夫です。
不安があるということは、それだけ真剣に向き合っている証拠。
だからこそ、完璧である必要はありません。
今のあなたにできることから、一歩ずつ。
自分のスタイルを大切にしながら、「自分らしい管理職像」を築いていくことで、きっとあなたらしく輝けるリーダーになれるはずです。
キャリアの選択肢が増えることは喜ばしいですが、自由度があるからこそ悩みも増えるもの。
特に女性は、仕事と家庭の比重が人によって大きく異なったり、ロールモデルが少ない分、どうするのがいいのか悩んで動けなくなる人も多いのです。
仕事に必死で押し殺して分からなくなった心の声をもう一度探し出し、何を選択すべきか見つけ出すには、キャリアコーチングがおすすめ。周りの声に惑わされず自分と向き合うことをサポートしてくれます。
キャリアコーチングは、時間が経って、状況や環境が変わっても、その思考プロセスや軸は、使い続けることが出来ます。
一生使えるスキルですので、どうせ自己投資するのであれば、少しでも早く、身につけた方が得です。
最近は、様々なキャリアコーチングが出てきていますが、キャリアだけでなく生き方も含めてしっかり向き合いたいなら、ポジウィルキャリアがおすすめ。
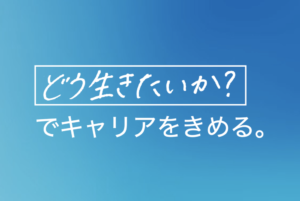
初回無料カウンセリングだけでも有料級の価値があると定評があります。
が、いつまでもカウンセリングが無料で受けれるとは限りません!今のうちに相談しましょう。
カウンセリングが無料で受けれるうちに相談