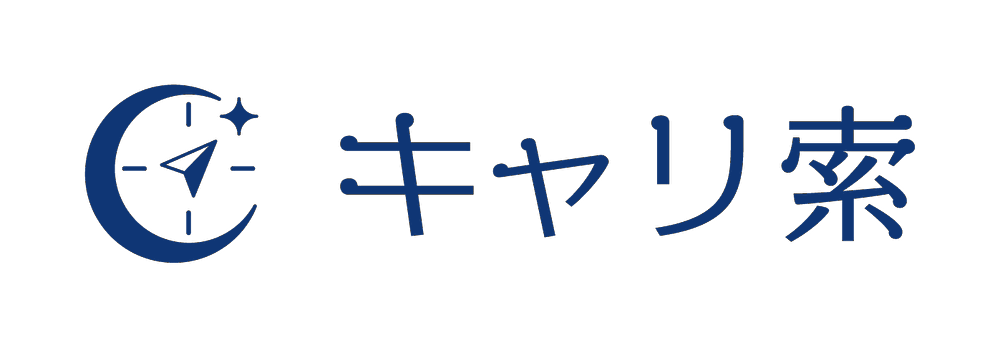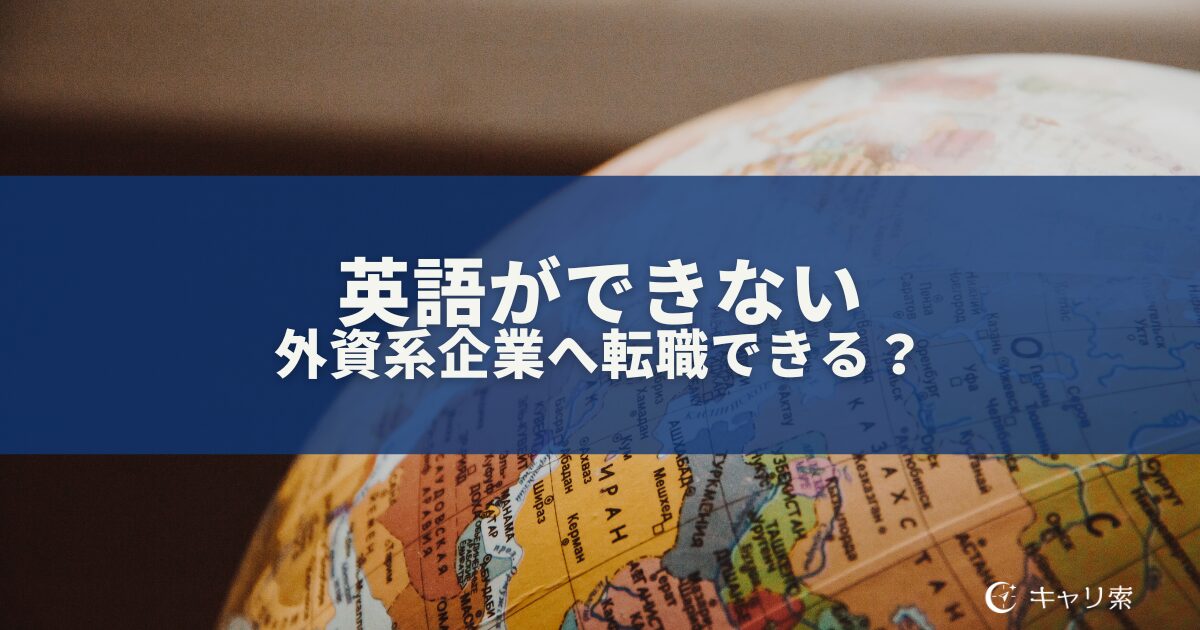「外資系企業って英語ができない人でも働ける?」
「外資系企業は英語できないとやっぱり苦労するよね?」
「外資系企業って英語力が不安でも転職できる?」
外資系企業=英語が必須というイメージが根強くありますが、実際には英語ができないことを理由に転職をあきらめる必要はありません。
外資系といっても企業のスタイルや部門によって求められる英語レベルは異なり、中にはほとんど英語を使わずに仕事をしている人も存在します。

私自身、外資系企業に勤めていますが、英語はほとんど使いません。
英語ができないことをハンデと捉えるのではなく、自分の強みをどう活かすかが転職成功のカギになります。
英語が得意ではなくても外資系企業で評価されるスキルを把握し、戦略的に準備すれば、外資系企業への転職は十分に実現可能です。
この記事では、英語力に自信がなくても外資系企業で求められる人材になるために意識したい5つのスキルとそれらがなぜ重視されるのかについて具体的に解説します。
業界や職種によって異なる英語使用の実態にも触れながら、今の実力で外資系を目指すための現実的なヒントをお伝えします。
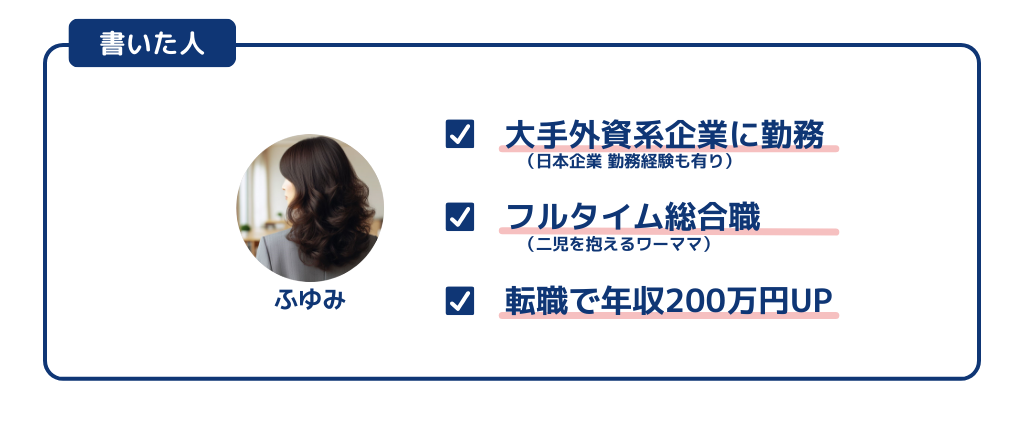
中途採用は新卒採用とは違い、ポジションが空いた瞬間や事業拡大など「今だけ」のタイミングで募集が出るケースがほとんど。
つまり、「理想の求人が出たら転職したい」と思っている人ほど、転職エージェントに登録しておくことが重要です。応募は断れますが、締切後の求人には二度と申し込めません。

待っていても”いい情報”は手に入りません。まずは登録しいい求人が届く状態をつくっておくことが、後悔のない転職の第一歩です。
▶︎車や家の購入で複数社の相見積もりを取るように、転職エージェント選びも比較が大切
複数のエージェントに登録しておくことで、担当者との相性、紹介される求人の幅、非公開案件の種類など、しっかり比較でき、納得できる転職が叶います。
理想の求人は、行動した人にだけ届きます。無料のサービスなのですから、後悔しない転職のためにいまの自分にできることを始めておきましょう。
| 転職サービス | 特徴 |
JACリクルートメント | 年収アップを目指すなら 登録しておきたい 外資系/グローバル企業に強い \ 筆者イチオシ / 無料相談する |
ロバートウォルターズ | 専門性×英語力を活かす 外国人コンサルタントが サポート 無料相談する |
ビズリーチ | 市場価値を知るなら 登録するだけで スカウトが届く 無料登録する |
英語できない人は本当に外資系企業に転職できない?
英語に自信がない状態で外資系企業への転職を目指すことに、不安を感じる人は少なくありません。
「外資=英語ができて当然」というイメージは根強くありますが、本当にそれだけが理由でチャンスをあきらめてしまって良いのでしょうか。
ここでは「外資系=英語必須」という固定観念を見直し、現実としての可能性を紐解いていきます。
英語ができないとは?外資系企業で求められる英語力は?
そもそも「英語ができない」とは、どのレベルを想定しているのでしょうか?
多くの人が不安に感じるのは、「TOEICのスコアが低い」「日常会話もままならない」「英語での電話応対に不安がある」など、ビジネスシーンでの英語対応への不安です。
でも実際には、外資系企業と一言で言っても、企業の業態や職種、ポジションによって、求められる英語力のレベルは大きく異なります。
たとえば、IT業界やコンサルティングファームの一部では、社内公用語が英語であることもあります。
資料作成や会議も英語で行われるため、高い英語力が求められます。
一方で、同じ会社の中でも国内営業やサポート部門、またはエンジニアの中でも社外とのやり取りが少ない開発担当であれば、英語を使う機会はかなり限られます。
また、製薬業界やメーカーなどでは、外資系といっても日本法人がほぼ独立して運営されているため、日本語だけで業務が完結することも多いです。
さらに、企業によっては英語でのやり取りが必要な場面でも、定型文のテンプレートや翻訳ツールが整備されていて、それを使いながら対応すれば問題ないというケースもあります。
つまり、英語力は「外資系だから必要」ではなく、「ポジションによって必要かどうかが違う」というのが正確な理解です。
これから外資系を目指す場合は、自分の希望職種が英語をどの程度使うのかを見極めることが大切です。
求人票や企業の情報だけでなく、転職エージェントを活用して詳しく確認するのも有効です。
無理に英語を武器にする必要はなく、自分の強みを発揮できる場所を見つける方が、転職成功の近道になります。
英語スキルがなくても採用されるケース
英語力が不問または初級レベルでOKとされる代表的なケースはこちらです:
- 日本市場向けの営業やカスタマーサポートなど、英語を使う必要がない職種
- 上司や同僚が日本人、社内資料や会話もすべて日本語で進む企業
- 日本支社の独立色が強く、日本語で完結する業務が中心
外資系企業でも、業務で英語を使わないポジションも多く、英語力がなくても働ける環境は想像以上にあります。日本のクライアント相手にする部署や日本国内で完結する部署であれば、業務中に英語を使う機会はほぼゼロということも珍しくありません。
例えば、私が働いている企業では、大企業なので同僚もレポートライン(上司たち)も基本日本語。社内の資料やメール、タウンホール(経営陣からの社内発表会議)まですべて日本語対応してくれているので、本当に英語を使いません。英語を使うのは年1回の本社レポート提出時くらいでした。
つまり、英語の読み書きや会話が全くできなくても、「大企業ですべて日本語対応されている企業」や「英語を使う機会がほぼない部署」であれば、問題なく採用されるケースも珍しくありません。
「英語できない=外資系は無理」という思い込みは捨てよう
外資系企業に対して「英語ができないと働けない」というイメージを持つ人は多いです。
この認識はある意味正しく、ある意味では誤解でもあります。
確かに、グローバルとのやりとりが日常的に発生するようなポジションでは、一定以上の英語力が求められるのは事実です。
たとえば、本社との定例ミーティングが英語で行われたり、海外チームとチャットでやりとりしたりする場面では、英語での意思疎通が不可欠です。
私自身、そういった会社で働いた事もあるので、英語力がないと苦労する外資系企業があることは理解しています。
しかし、すべてのポジションがそうではありません。
日本法人として独立して運営されている外資系企業も多く、そうした会社では日本市場を担当する部署や、ローカル業務に特化した部門であれば、日本語だけで完結するケースも少なくありません。

私の同僚でも、英語が本当に全く出来ない人も結構いて驚きました。しかし、仕事にはあまり支障はなさそうでした。
特に、最近はAIや自動翻訳も精度が上がっているので、英語力が無くても支障がない場合も増えているでしょう。
「英語が話せるに越したことはないが、必須ではない」というケースも多く、採用の判断も英語力以外のスキルに重点が置かれます。
つまり、「英語ができないから外資系には行けない」と決めつけてしまうのは、もったいないと言えるでしょう。
実際に英語力が低くても転職に成功した人のケース
英語力に自信がないまま外資系企業に転職し、その後も活躍している人の実例は少なくありません。
たとえば、ある30代前半の男性エンジニアは、TOEICスコアは550点程度で、英語の会話には苦手意識がありました。
しかし、日本国内の顧客向けに技術支援を行うポジションで採用され、専門的な技術力と現場経験が評価されました。
実際の業務では、海外の技術資料に目を通す場面もありますが、機械翻訳や翻訳ツールを使えば十分対応できるレベル。
社内会議は日本語、やりとりも日本人同士、英語の会話は年に1~2回あるかないか、という程度だそうです。
また、ある女性の営業職の方は、日系企業向けに製品を販売する営業担当として採用されました。
社内の資料は一部英語ですが、営業先はすべて国内企業で、業務はすべて日本語で行われているとのことです。
上司や同僚も日本人で、日本語でのコミュニケーションが中心です。
このように、英語が得意ではない人でも、自分の専門性や業務スキルを強みにして外資系企業に転職し、安定して活躍している人は多く存在します。
外資系企業で英語力よりも重視される5つのスキル
英語ができないと、外資系企業でのキャリアは難しいと思われがちです。
しかし実際の採用現場では、語学力だけで判断されることは多くありません。業務において求められるのは「実際に価値を出せるかどうか」です。
特に日本法人では、語学力よりも業務上のスキルや姿勢、人間関係を築く力が優先される場面も多く見られます。
この章では、英語力に自信がなくても外資系で活躍している人が持っている「英語以上に重視される5つのスキル」について、現場の実態も交えながら紹介していきます。
外資系企業英語力より大事なスキル①高い専門性や業務スキル
外資系企業では即戦力が好まれます。
つまり、「この人に任せればこの分野は安心」と思ってもらえる専門性があれば、語学力の不足を補えるだけの価値があります。
たとえば、IT系であればクラウド環境の構築経験、セキュリティ対応の実務、アーキテクチャ設計など。製薬業界なら薬事申請や臨床試験の運用経験。製造業ならばCADを使った設計や生産技術の経験がそれにあたります。
また、同じ分野でも「特定の技術やツールに強い」「顧客視点で考えられる」といった一歩先の知見があると、さらに強みになります。
英語が堪能な人が10人いても、その中に技術的な話ができる人が1人しかいなければ、その1人の市場価値は格段に高くなります。
外資系の選考では、職務経歴書や面接で「どんな経験があり、どんな価値を出せるか」が細かく問われます。
逆に言えば、「何ができるか」「何で会社に貢献できるか」を明確に示すことができれば、英語力に多少の不安があっても採用される可能性は高まります。
外資系企業英語力より大事なスキル②社内外の調整力・プロジェクト推進力
組織の中で複数の利害関係者をまとめながら物事を動かしていく力。
これは、外資系企業でも非常に重視されるスキルです。
実際の現場では、日本側の顧客、社内の営業、エンジニア、本社の企画担当など、様々な立場の人を巻き込みながらプロジェクトを進めていく必要があります。
そのときに必要なのは、「誰が何に困っているのか」「どの順番で話をつければうまく進むか」といった現場感と交渉スキルです。
仮に英語のやりとりが必要でも、専門用語やポイントを押さえて要点だけ伝えられれば十分に対応可能です。
特に日本法人では、「日本の顧客が求める細やかな対応を社内に落とし込む」ことが重要です。
こうした“翻訳的”な調整役になれる人材は、語学力よりもビジネススキルと信頼関係構築力が評価されます。
細かく気配りができる、関係者の立場を理解した行動ができる、問題発生時に先回りして調整できる。
そうした力は、外資系のスピード感ある現場でこそ、より価値を持ちます。
外資系企業英語力より大事なスキル③数字に対する意識や成果への執着
外資系企業の特徴として、「どれだけ努力したか」よりも「どんな結果を出したか」が評価される傾向があります。
これは評価制度にも明確に表れており、多くの企業がKPI(重要業績評価指標)やMBO(目標管理制度)で数字ベースの成果を求めます。
そのため、「売上をいくら伸ばしたか」「どの業務を何%改善したか」「コストをいくら削減したか」といった結果を、具体的な数字で語れる人材は高く評価されます。
英語が得意でも、成果を出せない人は評価されません。
一方で、英語が不得意でも、定量的な成果を出し続けている人は昇格・昇給の対象になります。
特に営業やマーケティング、企画、管理部門など、定量評価がしやすい職種では、成果に対する執着や数字への感度が重要になります。
また、業務改善やプロジェクト評価など、自分の成果を客観的に説明する力も、非常に大切です。
「頑張った」ではなく「成果を数字で示せる」こと。
これが外資系でのキャリアを築くうえで、語学力よりも強力な武器になるのです。
外資系企業英語力より大事なスキル④日本企業との橋渡しができる視点
外資系企業が日本市場で成果を上げるには、日本のビジネス文化や慣習を理解した人材が不可欠です。
実際、本社が意図するグローバル施策が、そのまま日本市場にフィットするとは限りません。
たとえば、欧米企業のスピード重視の営業手法が、日本の大手企業の稟議フローでは通用しないこともあります。
そのギャップを埋め、現場に合った提案に翻訳できる人材は、とても価値があります。
「日本の商習慣に精通している」「過去に日系企業との交渉をまとめた経験がある」などの実績は、まさに“橋渡し役”として評価される材料になります。
この役割は、英語の正確さよりも“相手の文化に配慮した伝え方”ができるかどうかが問われるため、語学力に不安があっても十分にこなせます。
むしろ「日本語で深いコミュニケーションができる」ことや、「両者の落とし所を見つけられる力」が求められます。
グローバルの方針を日本市場に最適化しながら、両者をうまくつなげる。
この力は、外資系にとって極めて重要なスキルです。
外資系企業英語力より大事なスキル⑤自発的に動けるセルフマネジメント力
外資系企業では、上司が細かく仕事の進め方を指示することはほとんどありません。
成果に向けて「自分で考えて動く」ことが前提となっているため、主体的に動けるかどうかが非常に重要です。
たとえば、「今この業務に何が必要か」「このタスクの目的は何か」を考え、自分でスケジュールを立てて行動できる人は、どの職種でも評価されます。
逆に、受け身で「言われたことだけをやる」という姿勢では、周囲からの信頼を得ることができません。
英語が得意でなくても、セルフマネジメントがしっかりできていれば、安心して仕事を任せられる存在になります。
また、わからないことを調べる、必要に応じて助けを求める、タスクの優先順位をつけて進めるといった行動も、外資系では当たり前とされる力です。
このように、「英語を話せるか」よりも、「自分の責任で仕事を進められるか」が問われる場面が多くあります。
自発性、判断力、行動力。この3つのバランスを持った人は、語学に頼らずとも高く評価される傾向があります。
外資系企業の中で英語をほとんど使わない職種・部門とは?
外資系企業=英語を使う環境というイメージは根強いものがありますが、実際には英語をほとんど使わないポジションも数多く存在します。
特に日本法人では、業務の大部分が日本語で完結する部門も珍しくありません。
ここでは、英語が苦手でも十分に活躍できる、英語使用頻度の低い職種・部門について解説します。
日本国内マーケット専任の営業・マーケティング
外資系企業でも、日本市場に特化した営業やマーケティングの仕事であれば、英語の使用は非常に限定的です。
なぜなら、顧客がすべて日本企業であるため、商談や提案、契約交渉はすべて日本語で行われます。
加えて、上司や同僚も日本人で構成されているチームであれば、社内コミュニケーションも日本語中心です。
資料作成に関しても、日本法人内のフォーマットやガイドラインに沿って作成するため、英語のアウトプットが求められる場面は少なくなります。
また、マーケティング職も国内向けキャンペーンや広告運用が中心であれば、外部とのやりとりは日本語で問題ありません。
英語の資料を読む必要がある場合もありますが、翻訳ツールを使って対応できるレベルであることがほとんどです。
このように、外資系でも「顧客が国内限定」というポジションは、実は非常に多く存在しています。
英語に不安がある人は、まずこうした営業・マーケティングの国内専任ポジションを探すと良いでしょう。
技術・エンジニア職(英語資料は多いが会話は少ない)
技術系職種、特に開発や設計、テクニカルサポートの分野では、「読み書きは必要でも、会話はほぼゼロ」というケースが多くあります。
たとえば、システム開発におけるコードや設計仕様書、海外製品のマニュアルなどは英語で書かれていることが一般的です。
ただし、それらは一度読めば理解できる定型文が多く、慣れてしまえば高い英語力は求められません。
また、翻訳ツールや社内のナレッジベースが整っていれば、英語の資料でも十分に対応できます。
加えて、日々の業務での会話は、日本人エンジニア同士、または日本法人内で完結することが多いため、スピーキングやリスニングの機会は限られます。
開発言語やツール、設計思想といった“技術の共通言語”がある世界なので、英語が流暢でなくても成果を出すことは十分可能です。
技術力を評価されやすい外資系では、英語よりも「何ができるか」「どんな課題を解決できるか」が重視されます。
コーポレート系職種(経理・人事など)は部門次第
経理や人事、法務などのコーポレート系部門も、会社によって英語使用頻度に大きな差があります。
特に、日本法人が独立しているケースや、本社との連携が限定的な場合は、日々の業務のほとんどが日本語で行われます。
たとえば、給与計算や社会保険手続き、勤怠管理などは、日本国内のルールに基づいて処理されるため、英語が関与する余地は少ないです。
また、法務部門も日本の法律に基づく契約審査やリーガルチェックが中心であれば、日本語の文書を扱うことがほとんどです。
人事業務でも、新卒・中途採用の選考対応や研修運営など、日本人社員向けの業務はすべて日本語で進められます。
ただし、月次報告や年次レビューなどで、レポートを英語で提出する必要がある企業もあります。
その場合でも、フォーマットや過去の事例を参考にすれば、テンプレート化されているため対応は難しくありません。
つまり、コーポレート職においても「どのような業務内容か」「本社との関係性はどの程度あるか」によって、英語使用の頻度は大きく変わるのです。

このように、英語を使わずに済む職種・部門は意外と多く存在しています。
求人を探す際には、「誰を相手にする仕事か」「社内外の関係者に英語話者がいるか」「英語を使うシーンは業務の中でどの程度あるか」といった視点で見ていくことが重要です。
英語が出来ないけど外資系で働きたいなら大企業がおすすめ
英語に自信はないけれど、待遇やキャリアの観点から外資系企業に興味がある。そんな人は意外と多いものです。
実際、外資系企業は年収が高く、評価もフラットで成果主義。自分の力でキャリアアップを目指したい人にとって魅力的な環境です。
しかし、「英語ができないから無理かもしれない」と、一歩を踏み出せない人もいます。
そんなときに意識したいのが、「企業の規模」です。
大手の外資系企業には“英語に頼らずに働けるポジション”や“安心して働ける仕組み”が整っているという事実です。
ここでは、大企業の外資系企業がなぜ英語力に不安がある人にとっておすすめなのか、その理由を詳しく解説します。
日本人部門だけで仕事が完結する部門が多い(英語力はほぼ不要)
大手の外資系企業では、日本市場向けに専用の部門やチームが設けられているケースが非常に多く見られます。
たとえば、日本国内の顧客を対象とした営業部門、日本人社員中心で構成されたマーケティングチーム、国内向けのテクニカルサポート部署などです。
こういった部署では、日々のやりとりも資料もすべて日本語で完結するため、英語を使う場面はほとんどありません。
また、社内でも日本人の上司・同僚と仕事を進める場合が多く、外資系でありながら働く環境は日系企業とほとんど変わらないと感じる人もいます。
中には「入社して1年たつけど、英語のメールは1通も書いていない」という社員もいるほどです。
特に、日本法人が独立採算制をとっているような企業では、日本チームが意思決定権を持ち、日本の市場ニーズに応じて柔軟に動ける体制が整っています。
英語を必要としないロールや案件を希望すれば、英語力が原因で足踏みする必要はまったくないのです。

私も最初に入った部署は英語を使う機会がほぼ無く、外資系企業に入って、逆に英語力が落ちました(苦笑)。
社内カンファレンスや社内文書にも日本語通訳や日本語版がある場合がほとんど
大企業の外資系企業では、社員が言語の壁を感じずに働けるよう、多言語への対応が非常に充実しています。
たとえば、グローバル本社からのビデオメッセージや重要な社内アナウンスは、字幕付き動画で配信されたり、要点をまとめた日本語版の資料が用意されることが多くあります。
年に1回の全社会議(タウンホール)では、同時通訳が入ることも一般的です。
また、社内イントラやナレッジポータルでも、日本語ページが整備されており、操作ガイドやFAQ、手順書なども日本語で提供されています。
社内に日本語を扱うローカルのサポートチームが常駐しているケースもあり、「英語が読めなくて困った」ときにも、すぐに相談できる体制が整っています。
こうした取り組みは、単に言語面の不安を軽減するだけでなく、「言語がハンディにならないように全社員に機会を平等に与える」というグローバル企業ならではの配慮なのかなと思います。
英語が苦手でも、理解すべき情報が日本語で届けられる安心感はとても大きく、業務への集中度も高まります。
「外資系だから英語ばかり」という不安は、実は入社してみると意外にも解消されるケースが多いのです。
ツールなどを駆使すれば乗り切れることも多い
テクノロジーの進化も、英語に自信のない人の強い味方になっています。
今では、Google翻訳やDeepLといった翻訳ツールの精度が非常に高く、メール文面や資料の内容もかなり正確に翻訳できます。
英語で届いた資料を読み込む際も、コピペして翻訳ツールに入れれば、大まかな内容は問題なく把握できます。
さらに、ZoomやTeamsなどの会議ツールでは、リアルタイムで字幕や翻訳が表示される機能も普及しています。
「発言の意味が分からない」と感じても、ある程度補足しながらキャッチアップできるのです。
実際の現場では、英語が得意なメンバーがフォローしてくれたり、チーム内で日本語に訳して共有する文化がある職場も多くあります。
また、社内でも「わからない部分は翻訳ツールを使ってでも対応しよう」というスタンスが一般的になっており、英語に完璧さを求められる空気はかなり薄れています。
重要なのは、「わからないから避ける」ではなく、「わからないから工夫して対応する」という前向きな姿勢です。
実際、英語が苦手だった社員が、ツールや仲間の助けを借りながら少しずつ成長し、1年後には英語での簡単なやりとりができるようになったという例もあります。
「完璧にできなくてもいい、やる気があるなら支える仕組みがある」というのが、大企業の外資系の良いところです。
外資系企業で英語ができないと損する?デメリットは?
英語を使わずに働けるポジションや環境がある一方で「英語ができないまま働き続けることによるデメリット」も確かに存在します。
英語が苦手でもスタート地点に立つことは可能ですが、長期的にキャリアを築いていく中で、英語力が壁になる場面も出てくるのが現実です。
ここでは、英語ができないことが業務やキャリアに与える影響を、具体的なシーンごとに解説していきます。
外資系で英語ができないデメリット①アサインや仕事内容が制限される
英語が苦手な場合、関われる仕事の範囲が限られることがあります。
たとえば、グローバルプロジェクトへの参加、海外拠点との協業、本社レポート作成など、「英語でのやり取りが前提」の業務にはアサインされにくくなります。
外資系企業では、プロジェクトベースで人材がアサインされることも多く、「英語対応が可能な人」に優先的に声がかかる傾向があります。
その結果、興味がある分野の仕事に関われなかったり、自分の成長機会が減ってしまうこともあり得ます。
また、特に若手〜中堅のうちは「いろいろなプロジェクトに関わって経験を積む」ことが評価につながるため、英語力の不足がキャリア初期の広がりを抑えてしまうこともあるのです。
やりたい仕事が英語を前提にしている場合、そのチャンスを逃すことになってしまう可能性もあるため、一定の英語力はやはり武器になります。
外資系で英語ができないデメリット②キャリアアップに影響する
外資系企業では、一定の職位以上になると、英語が実質必須になる場面が増えていきます。
たとえば、マネージャー職になると、本社へのレポーティングや、他国のチームとの調整業務が発生するようになります。
また、グローバルの経営会議に参加したり、海外出張が発生する場合もあり、ある程度の英語でのコミュニケーション力が求められます。
このため、現場レベルでは評価されていても、「英語が話せないから昇格は難しい」と言われてしまうケースは実際にあります。
本人にとっては悔しい話ですが、企業としても一定の英語対応力がないとマネジメントを任せられない、という判断を下すのは当然の流れです。
特に、グローバルとの連携が多い業界や企業では、「部長になるには英語面接が必須」「役職者は海外と定例でつながる」といった仕組みが整っているところもあります。
つまり、英語力がキャリアの上限を決めてしまうリスクがあるのです。
もちろん、逆に言えば「英語力がある人は昇進しやすい」ということでもあり、英語を武器にできれば上を目指しやすい環境でもあります。
外資系で英語ができないデメリット③仕事の効率が下がる
英語ができないことで、日々の業務の効率が下がってしまうケースもあります。
たとえば、グローバルから送られてくる資料やマニュアルがすべて英語で、そのたびに翻訳ツールに頼らなければならない。
チャットやメールのやりとりに時間がかかってしまい、返信が遅れてしまう。
会議での発言内容が聞き取れず、あとから周囲に確認しないといけない――こうした小さなロスが積み重なると、他のメンバーとの「見えない差」になります。
特にスピード感が重視される外資系企業では、情報を素早くキャッチし、即対応することが評価されやすいため、「読み書きに時間がかかる」というだけでも不利になることがあるのです。
また、自分では理解したつもりでも、ニュアンスを誤解していた、背景を読み取れなかった、ということも起こりがちです。
英語が少しでも使えれば、このようなストレスを軽減でき、周囲との協業もしやすくなります。
完璧な英語力は必要ありませんが、最低限「伝える・読む・理解する」力があると、日々の業務がスムーズになります。
外資系企業で英語力を高めながら働くには?
英語力に不安があっても、外資系企業で働きながら少しずつ成長していくことは十分に可能です。
実際、入社時点では英語に苦手意識を持っていた人が、日々の仕事や環境を通じて英語力を高め、数年後にはグローバルプロジェクトで活躍するようになったというケースも多く見られます。
ここでは、英語が苦手な状態から少しずつレベルアップしていくための現実的な方法や、外資系企業ならではの環境の活かし方について紹介します。
実践で少しずつ身につける方法
英語学習のモチベーションが続かない、という声は少なくありません。
だからこそ、無理に時間を作って学ぶのではなく、日々の業務の中で少しずつ「実務の中で英語に触れる」ことが上達の近道です。
たとえば、英語のメールを読むとき、まずは翻訳ツールに頼るのではなく、自分で読んでみてから翻訳を確認する。
会議中の英語のフレーズでよく使われるものをメモして、自分でも使ってみる。
英語のマニュアルや報告書に出てくる単語をストックして、日常的に目にするようにする。
こうした“生活の中で覚える”感覚が、英語を定着させるポイントです。
また、業務に関係のある語彙は、何度も出てくるため記憶にも残りやすく、机に向かって単語帳を開くよりもはるかに実践的です。
自分の仕事に関連した英語から入ることで、無理なく自然と語彙や表現が身についていきます。
英語を“学ぶ”のではなく、“仕事の一部として使う”という感覚で少しずつ取り入れるのがコツです。
英語を学びやすい社内制度・研修を活用する
多くの外資系企業では、社員の英語力を高めるための研修制度やサポート体制が整っています。
たとえば、オンライン英会話レッスンの費用補助や、語学スクールとの提携、TOEIC受験料の補助など、学ぶ意欲がある人を後押しする仕組みがあります。
なかには、勤務時間内に受講できる英語トレーニングを提供している企業もあり、日常業務と両立しながら学べる環境が整っています。
また、グローバル本社との会議や海外の同僚とのやりとりが発生するポジションでは、自然と英語を使う機会が増えます。
最初は聞き取れなかった言葉も、繰り返し聞くうちに理解できるようになり、自分でも簡単な表現ができるようになるなど、業務を通じて実践的に英語が身についていきます。
さらに、企業によっては「英語学習コミュニティ」が社内にあり、社員同士で英語を学び合ったり、英語で雑談する「English Café」が開催されているケースもあります。
こうした社内の取り組みを積極的に活用することで、自然と英語への抵抗感が薄れていきます。
学習意欲があれば、外資系企業はその背中をしっかり押してくれる環境だと言えるでしょう。
英語力が伸びる人に共通する行動パターン
外資系企業で働く中で、英語力がどんどん伸びていく人にはいくつかの共通点があります。
まず、「失敗を恐れずに話す」こと。
文法や発音の間違いを気にしすぎず、とにかく伝えることを重視して英語で発言する姿勢は、上達のスピードを加速させます。
次に、「繰り返し使う」こと。
メールや会議、チャットなど、日々の業務の中で同じようなフレーズを繰り返し使うことで、表現が自然と自分のものになっていきます。
さらに、「自分の関心があるテーマで英語に触れる」ことも大切です。
たとえば、ITエンジニアであれば海外の技術カンファレンスの動画を見る、マーケターであれば海外事例のWeb記事を読む、など、日常的に“興味のある英語”をインプットに使うと学習効果は高まります。
英語を勉強として捉えるよりも、「必要だから使う」「面白いから読む」といった、自然な接し方が続けやすさにもつながります。
最後に、素直に「わからない」と聞けることも大切な姿勢です。
英語が苦手なうちは、聞き返すことに躊躇してしまいがちですが、意外と相手もゆっくり話してくれたり、繰り返してくれたりします。
その経験を通じて、「話しても大丈夫なんだ」「伝わることが大事なんだ」と実感でき、英語へのハードルが下がっていくのです。
まとめ:英語ができなくても外資系転職は可能。大事なのは“武器”を持つこと
「外資系=英語ができる人の職場」というイメージに、不安を感じている人は少なくありません。
しかし実際には、英語が苦手でも外資系企業で働いている人は多く、自分の専門性やビジネススキルを武器に、活躍しているケースが数多くあります。
重要なのは、“英語ができるかどうか”ではなく、“英語以外で何を提供できるか”という視点です。
専門性、実績、調整力、主体性、数字へのこだわり――こういったスキルや姿勢は、語学力以上に評価されることも少なくありません。
また、英語を使わない仕事や環境を選ぶことで、語学力に頼らずキャリアを築くことも十分に可能です。
とくに、大手の外資系企業には、日本語中心で完結できる部署や、翻訳や通訳のサポート体制が整った職場も多く、英語が苦手な人にとって働きやすい環境が用意されています。
一方で、将来的なキャリアアップや業務範囲の拡大を考えるなら、少しずつでも英語力を高めていくことが望ましいのも事実です。
英語を使う場面で困らない程度のリーディング力や、簡単な表現で伝えられる会話力があれば、チャンスの幅は確実に広がります。
完璧な英語を話せなくても大丈夫です。
大切なのは、「できないから無理」と決めつけるのではなく、「今の自分にできることを伸ばす」「必要なことは少しずつ身につける」という前向きな姿勢です。
外資系企業は、“結果で評価される”環境だからこそ、英語に自信がなくても実力でチャンスを掴むことができます。
不安を感じている段階でも、一歩踏み出す価値は十分にあります。
自分の強みを理解し、無理のない範囲でスキルと向き合っていけば、語学力に不安があっても、外資系でキャリアを築いていくことは可能です。